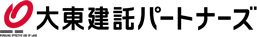
住まいと健康の
お役立ちコラム
住まいに寄り添う健康情報の発信
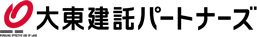
住まいに寄り添う健康情報の発信


健康寿命を延ばして、より豊かに暮らしませんか?健康寿命とは心身ともに自立し、いきいきと生活ができる期間のことをいいます。WHO(世界保健機構)や厚生労働省によりますと、日本における2018年の平均寿命は84.2歳であるのに対して健康寿命は74.8歳とされ、約10年間は介護などのサポートを受けなければ生活しにくい期間といわれています。大東建託パートナーズでは、健康的で豊かな暮らしをより長く続けられるお手伝いをさせていただきたく、健康情報の発信をしています。

前回、住まいに潜む転倒リスクについてお伝えさせていただきましたが、転倒は歯の健康と関連性があることをご存知でしょうか。
ある研究では、歯が少なく義歯などを入れてない人は、そうでない人と比較して、転倒のリスクが高くなるということがわかっています。そのリスクは最大2.5倍になるといわれており、これには「噛み合わせ」が関係しています。左右の奥歯でしっかりと噛めない、いわゆる噛み合わせが悪くなることで、体のバランスをとることが難しくなります。さらに、噛み合わせが悪いと、フラついた時にも踏ん張ることができず、転倒のリスクが高まってしまうのです。
また、認知症の発症リスクについても似たような研究結果があり、そのリスクは最大1.9倍になるといわれています。私たちの脳は、噛むことで多くの刺激を受け、たくさんの血液が流れ込むことで、その働きが活発になります。そのため、噛み合わせが悪くなったり、噛む力が弱くなったりすることで脳への血流が減り、認知症になるリスクが高まるのです。
令和4年の日本の平均寿命は女性87.09年、男性81.05年となっており、女性は1位、男性は4位と、日本は世界的な長寿国であることを示しています。1989年から厚生労働省が提唱している「8020運動」(80歳になっても自分の歯を20本以上保とうという運動)の推進により、8020達成者は51.6%にまで上昇しました。しかしながら、歯の先進国といわれるスウェーデンでは80%となっており、日本人の歯の本数は長寿に追いついていない現状となっているのです。
私たちは中高年以降、急速に歯を失っていく傾向があります。自分の歯をできるだけ多く残すためにも、若いうちから、かかりつけの歯科で定期的なチェックを受ける習慣をつけることが非常に重要です。また、冒頭の研究結果からもいえるように、たとえ歯が19本以下であっても、きちんと義歯などを使用している場合は、転倒や認知症のリスクを低減させることができるのです。歯を失ったとしても、歯がない状態や、噛みにくい状態を放っておくのは危険です。義歯などの人工物で補い、機能が落ちないようにすることも、健康寿命を延ばす上で重要なポイントとなるでしょう。
健康寿命を延ばすためには、歯のメンテナンスが大切ということがわかりましたが、日々の口腔ケアを行うことは、がん予防にもつながります。今は2人に1人ががんになる時代と言われており、身近な病気になっているがんですが、歯を磨く回数や歯周病の有無もがんの発症に関係しているのです。

右の図のように、1日に2回以上歯を磨く人は、1回の人と比べて、口の中や食道のがんにかかるリスクが3割も低くなり、逆に全く磨かない人のリスクは1回磨く人より1.8倍、2回の人より2.5倍にまで高くなることがわかっています。また、歯の数とがんのリスクとの関係についても調査されており、歯の数が減るほど、食道がんが増えることもわかっています。歯が9~20本の人では、21本ある人に比べて、食道がんのリスクはそれほど増えませんが、1~8本の人では1.9倍に、1本もない人では2.4倍にまで上昇していたのです。
毎日の歯磨きは歯周病の予防にも効果的です。歯周病は、口の中だけでなく、糖尿病をはじめ、狭心症や心筋梗塞などの心臓、脳梗塞などの脳血管にも悪影響を及ぼすことはご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、がんにも関連していることがわかってきています。是非この機会に、ご自身の口腔ケアについて振り返ってみていただければと思います。
今回は、定期的な歯科受診と毎日の口腔ケアについてご紹介しました。これらのような情報が、みなさまの充実したセルフケアにつながり、生活がより豊かなものとなられましたら幸いです。
作成:大東建託パートナーズ株式会社 人事部健康経営課 保健師 飯塚祐美恵
監修:株式会社Studio Gift Hands 産業医・労働衛生コンサルタント 三宅琢
(2024年2月29日)
●参考資料
日本歯科医師会 テーマパーク8020:https://www.jda.or.jp/park/relation/teethlife.html (2024年2月6日アクセス)
がん対策推進企業アクション ポストコロナの職域がん対策 vol.9
●産業医と保健師による情報の提供は、診断・治療行為ではありません。診断・治療を必要とする方は、適切な医療機関での受診をおすすめいたします。また、掲載内容は作成者個人の見解によるものであり、全ての方への有効性を保証するものではありません。当コラムで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いかねます。
10月10日は転倒の日ですが、実は高齢者の転倒事故の約半数が、住まいで起こっていることをご存知でしょうか。転倒に伴う怪我は、「擦過傷、挫傷、打撲傷」に次いで「骨折」が多いことがわかっています。さらに骨折をした場合、76%の方で入院が必要となっています。骨折の症状が軽くても、若いときに比べると治癒に時間がかかり、想定よりも入院期間が長くなってしまうこともありますし、これらが原因となって、介護が必要な状態になることもあります。
このように転倒事故は、ご自身の心身・生活だけでなく、場合によってはご家族の生活にも影響を及ぼすなど、深刻な状況を引き起こします。
そこで今回は、住まいに潜む転倒事故のリスクと、予防のための注意点をご紹介させていただきます。
年齢を重ねることを止めることはできませんが、生活を工夫することで、年とともに健やかで心豊かに実りある日々を過ごすことができると考えています。この機会に、ご自身やご家族の住まいを振り返ってみてはいかがでしょうか。
作成:大東建託パートナーズ株式会社 人事部健康経営課 保健師 飯塚祐美恵
監修:株式会社Studio Gift Hands 産業医・労働衛生コンサルタント 三宅琢
(2023年9月30日)
●参考資料
消費者庁 : https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_040/
(2023年9月12日アクセス)
●産業医と保健師による情報の提供は、診断・治療行為ではありません。診断・治療を必要とする方は、適切な医療機関での受診をおすすめいたします。また、掲載内容は作成者個人の見解によるものであり、全ての方への有効性を保証するものではありません。当コラムで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いかねます。
この冬は10年に一度と言われる大寒波が到来しましたが、日本は季節の影響を受けて起こりやすい雨やそれに伴う洪水、土砂災害に加えて、季節を問わず起こる地震や津波など、自然災害の多い国です。また、災害によっては被害が広域・長期に及ぶこともあります。これまでの経験や情報から、常日頃より防災を意識して生活されている方も多くいらっしゃるかと思いますが、今回は、住まいを脅かす災害時の健康障害についてお伝えします。
災害時には停電や断水の影響による水不足やトイレが使えないこと、また、避難所生活で、トイレに行きづらいなどの理由から、なにかと水分摂取を控えようとしがちです。
しかし、ご存知のように、わたしたちのからだの60%は水分でできており、体重の3%に相当する水分が喪失すると脱水症状が表れるといわれています。災害という非常事態ともなればストレスなどの心的要因も加わり、災害時の復旧作業などで体を動かした場合は、さらに脱水のリスクが高まります。熱中症の予防と同じく湿度や温度が高い時期はなおさら注意が必要です。
このように、災害時は脱水のリスクが高くなるということを意識して、こまめに水分をとるよう心がけることが大切です。特に高齢の方は脱水に気付きにくく、こうした影響を受けやすいため、尿路の感染症や心筋梗塞、エコノミークラス症候群などを引き起こすリスクが高まります。しっかりと水分をとるように心がけるとともに、脱水になりやすいとされる家族や周囲の人には、声掛けを行いましょう。
飛行機などに長時間乗っていることでリスクがあるといわれているエコノミークラス症候群ですが、実は災害時にもリスクが上がることがわかっています。災害時、食事や水分を十分にとらない状態で、車などの狭い座席に長時間座っているなどして足を動かさないと、血行不良が起こり、血液が固まりやすくなります。その結果、血の固まり(血栓)が足などにでき、痛みや腫れが生じることがあります。また、この血栓が肺などに飛び、血管を詰まらせることで、胸が痛い、呼吸が苦しいなどの症状をおこし、時には命の危険もある病気を引き起こすことがあります。
そのため、狭い車内などで寝起きを余儀なくされているときは、注意が必要です。予防のためのポイントをまとめましたので、是非ご参考になさってください。
胸の痛みや、片側の足の痛み・赤くなる・むくみがある場合は、早めに医師に相談して下さい。






今回は自然災害に関連する健康障害についてお伝えさせていただきました。いつ訪れるか分からない災害だからこそ、普段からのモノ・知識の備えが自分や家族を守ることになります。大東建託パートナーズでは、暮らしに役立つプラットフォーム「ruum」でも、防災情報や防災に関連するサービスのご紹介を行っております。皆様の住まいと健康がより充実したものになりますと幸いです。
作成:大東建託パートナーズ株式会社 人事部健康経営課 保健師 飯塚祐美恵
監修:株式会社Studio Gift Hands 産業医・労働衛生コンサルタント 三宅琢
(2023年2月1日)
●参考資料
厚生労働省 被災地での健康を守るために:
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/hoken-sidou/disaster.html
(2023年2月1日アクセス)
厚生労働省 エコノミークラス症候群予防のために:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170807.html
(2023年2月1日アクセス)
●産業医と保健師による情報の提供は、診断・治療行為ではありません。診断・治療を必要とする方は、適切な医療機関での受診をおすすめいたします。また、掲載内容は作成者個人の見解によるものであり、全ての方への有効性を保証するものではありません。当コラムで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いかねます。
コロナが流行し始め早4年目、非常事態宣言における行動制限から始まった新しい生活スタイルはいつしか私たちの日常となりつつあります。新しい日常では外出はままならず在宅時間が増える傾向にあり、住まいをより快適にアレンジして暮らしに彩りを添えられている方が多いかと思います。住まいのアレンジに加えて自分をととのえ、暮らしにメリハリをつけることを加えてみてはいかがでしょうか?
『令和3年度スポーツの実施状況等に関する世論調査』(スポーツ庁、2021)によると、体力に不安があり運動不足を感じながらも運動習慣を変えられない、自分の体力に不安があると感じている方々が多いことがわかります。つまり、運動習慣がなかなか身につけにくい現状が浮かび上がります。
☆「体力に不安がある」51.2%
☆「普段運動不足を感じる」77.9%
☆「1年前と比べて運動・スポーツの実施頻度はあまり変わらない・変わらない」55.6%
実は「運動・スポーツをもっとやりたいと思う」割合は47.3%と高く、運動に関心を持っている方々は多いことがわかります。直近の1年間で行った運動・スポーツの種目については「ウォーキング」が 64.1%と高い割合を占め、「ウォーキング」は誰もが始めやすい運動であることがわかります。
手軽に始められそうな「ウォーキング」の効果にはどんなものがあるのでしょうか?
☆効果的なウォーキングは脂肪を燃焼させ、体型をととのえることができます。全身の血液循環の滞りを改善し、筋力を保持・増強します。筋力増強は基礎代謝量と一日の消費エネルギー量を増やすことから、太りにくい体を手に入れることにつながります。
☆ウォーキングは呼吸をしながら行う運動であるため、呼吸機能の保持・改善をすることができます。
☆適切なウォーキングは骨にほどよい負荷をかけ骨の再生を促すため、骨粗鬆症を予防し、寝たきりを防ぎます。
☆アメリカの18歳以上の糖尿病患者2896名のうちウォーキング習慣がある糖尿病患者では、ウォーキング習慣のない患者と比べ死亡率が低下した。最も死亡率が低かったのは1 週間に3 ~4 時間歩く人だった。(Gregg ら、2003)
☆イタリアの65 歳以上の749 人のうちウォーキング習慣がある人や日常生活でよく身体を動かす人は、認知症のリスクが7 割以上も低下した。(Ravagliaら、2007)
今回は暮らしにメリハリをつける自分をととのえる方法としてウォーキングをご紹介しました。ウォーキングを取り入れられることがみなさまの充実した心と体のセルフケアにつながり、住まいでの時間がより豊かなものとなられましたら幸いです。
作成 : 大東建託パートナーズ株式会社 人事部健康経営課 産業保健師・健康経営エキスパートアドバイザー 印東桂子
監修 : 株式会社Studio Gift Hands 産業医・労働衛生コンサルタント 三宅琢
(2022年9月16日)
●引用・参考資料
Edward W. Gregg et al(2003):Relationship of Walking to Mortality Among US Adults with
Diabetes, Archives of Internal Medicine, Vol.163, 1440-1447.
F. Ravaglia et al(2007): Physical activity and dementia risk in the elderly. Findings from prospective Italian study, Neurology.
厚生労働省(2008):健 康 増 進 の ラ イ フ ス タ イ ル形成支援・連携方策に関する調査報告書、第1章 「歩く」効果・効用とそれを習慣化する方法の整理
https://www.mlit.go.jp/common/000022977.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjlwp_J3pj6AhVOm1YBHffjCT0QFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw09f4dN0oaKEk6x5_kNq2qM
スポーツ庁(2021):令和3年度スポーツの実施状況等に関する世論調査
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/sports/1415963_00006.htm
●本情報の提供は、診断・治療行為ではありません。診断・治療を必要とする方は、適切な医療機関での受診をおすすめいたします。また、掲載内容は作成者個人の見解によるものであり、全ての方への有効性を保証するものではありません。当コラムで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いかねます。
COVID-19感染症の猛威から私たちの生活スタイルは変わり、もう2年が経とうとしています。住まいでのテレワークである、在宅勤務にはもう慣れたでしょうか?この就業スタイルは緊急事態宣言・まん延防止重点措置が全国的に解除されても、私たちの生活スタイルとして残っていくと考えられています。そう、自分好みのワークライフバランスに合わせて、在宅勤務と職場勤務から働き方をカスタマイズしていく時代をむかえようとしているのです。もしかしたらあらゆる場所がオフィスになる、そんな時代も訪れるかもしれませんね。
在宅勤務が広がることにより、セルフケアへの関心が高まっていると言われています。これはなぜでしょうか?
COVID-19感染症の拡大は、私たちが当たり前だと気にもしていなかった生活スタイルを一変させました。その結果、日々の行動範囲を自粛しながら、今まで経験しなかった不安や焦り、孤独感を感じ、心身のバランスの乱れを感じる方々が少なくありませんでした。また、在宅勤務によって削減された通勤時間を自分の時間として活用し、心身のバランスをより整えていく方々も多くいらっしゃいました。これら変化が自分自身を整えていることへの、言い換えるとセルフケアへの関心を高まらせていったのでしょう。
私たちができるセルフケアにはどのようなものがあるでしょうか?今回は、住まいでできる部屋の明るさの調整についてお伝えします。
睡眠中の部屋の明るさに気を付けましょう
夜、眠っている間、照明をつけたまま光を浴びて眠ると、肥満症・脂質異常症になる方が約2倍も増えたと報告されています(Obayashi、2013)。これは睡眠中の夜間に人工照明の光を浴びることによって、体内時計を狂わせてしまうことが原因になっていると考えられています。私たちは日中に屋内で過ごすことが多いため日中の光曝露が少なく、夜間に人工照明を使用するために夜間の光曝露が多い傾向があるのです。
ポイント1
部屋の照明を外の明るさに合わせて、外が暗くなっていたら照明の明るさを1段階下げたり、照明の調光機能を使用して照明の明るさや色味を変えたりすることがおすすめです。
ポイント2
就寝2時間前からスマホやパソコン、テレビの画面を見るのをできるだけ止め、夜間のブルーライト暴露を避けましょう。ブルーライトは脳を覚醒させてしまうため、寝付きにくくします。
ポイント3
睡眠中はできるだけ明かりを消しましょう。もし、トイレなどで夜中に起きる必要がある方や、子どもさんや家族のお世話が必要な場合は、視界に入らない場所に常夜灯やフラットライトを活用しましょう。
ポイント4
朝、起床したら太陽光を感じて、体内時計の乱れを整えましょう。朝、レースのカーテン越しの日光で部屋が明るくなるのを感じるだけでも、体内時計をリセットすることができると言われています。朝起きるのが苦手な方はタイマーに合わせてカーテンを自動的に開けてくれるコンパクトに設置できる機器や起床時間に合わせて徐々に照明を明るくしていく機能のある目覚まし時計や照明を導入されてもいいかもしれません。
目の疲れを軽減できるように、仕事する部屋の明かりを見直してみましょう。部屋が暗すぎてパソコンの画面が見にくいと姿勢が乱れ、目の疲れだけでなく肩こりや腰痛も引き起こしてしまいます。これらを予防するために、厚生労働省の「自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備」「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」にはセルフケアの方法が紹介されています。在宅勤務でも、照度を整えることで労働生産性が向上することが報告されています(Okawara, et al. 2021)。
ポイント1
できるだけ室内の明暗差が少なく、まぶしさを生じないように、パソコン画面上の照度は500ルクス以下、書類上やキーボード面の照度は300ルクス以上を目安としましょう。
無料の照度計アプリを活用して、ぜひ部屋の照度を確認してみてください。
ポイント2
パソコン画面の明るさや書類等の明るさと周辺環境の明るさにできるだけ差がないようにしましょう。画面に太陽光が入ってしまう場合はカーテンやブラインドなどで見やすいように調整しましょう。間接照明などのグレア※防止照明器具を活用するのもおすすめです。
※グレア…良好な見え方を邪魔するもので,不快感や物の見えづらさを生じさせるような「まぶしさ」を指します。
これらのような住まいの光の工夫の情報が、みなさまの充実したセルフケアにつながり、在宅勤務での時間がより豊かなものとなられましたら幸いです。
作成 : 大東建託パートナーズ株式会社 人事部健康経営課 産業保健師 印東桂子
監修 : 産業医科大学 環境疫学研究室 教授 藤野善久
(2021年10月12日)
●引用・参考資料
Kenji Obayashi, Keigo Saeki, Junko Iwamoto, et al.(2013):Exposure to light at night, nocturnal urinary melatonin excretion, and obesity/dyslipidemia in the elderly: a cross-sectional analysis of the HEIJO-KYO study、J Clin Endocrinol Metab.doi:10.1210/jc.2012-2874.
Okawara, M., Ishimaru, T., Tateishi, S., Hino, A., Tsuji, M., Ikegami, K., Nagata, M., Matsuda, S., Fujino, Y., & CORoNaWork project. (2021). Association Between the Physical Work Environment and Work Functioning Impairment While Working From Home Under the COVID-19 Pandemic in Japanese Workers. Journal of Occupational and Environmental Medicine / American College of Occupational and Environmental Medicine, 63(9), e565?e570.
厚生労働省(2021):自宅などでテレワークを行う際の作業整備、
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01603.html
厚生労働省(2021):テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
●本情報の提供は、診断・治療行為ではありません。診断・治療を必要とする方は、適切な医療機関での受診をおすすめいたします。また、掲載内容は作成者個人の見解によるものであり、全ての方への有効性を保証するものではありません。当コラムで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いかねます。
暖冬と言われたこの冬も、年が明けるとすっかり冷え込んできました。今回は寒い冬の時期を快適に、そして健康に過ごせるような情報をお伝えします。
お部屋では暖房器具を使う方も多いかと思いますが、併せて湿度をコントロールすることも重要です。同じ温度でも湿度30%の場合と50%の場合では、後者の方が温かく感じるということがわかっています。つまり、湿度を上げることで体感温度が上がり、過ごしやすく感じることができるのです。
ご家庭での湿度の目安は40~60%とされており、湿度が60%以上ですとカビやダニなどが発生しやすくなり、逆に40%以下になると目や肌、のどに乾燥を感じたり、インフルエンザウイルスが活性化されたりします。室温と湿度をうまく調整して、快適な冬を過ごしましょう。
ちょっとした工夫で体感温度を上げることができます。
ポイント1体温を上げる
マフラー・手袋・レッグウォーマーを活用し、3つの首といわれる「首・手首・足首」を重点的に温めましょう。また、太い血管のあるところや、僧帽筋のような大きな筋肉のある肩甲骨を温めると、血液の循環もよくなり冷え性などにも効果があります。
ポイント2湿度を上げる
加湿器を併用したり洗濯物を室内に干したりすることでお部屋の湿度が上がり、より快適に過ごせます。
ポイント3室内環境の見える化を
お部屋に温度計や湿度計を置くことで、お部屋の環境が見える化され、室内の温度や湿度の変化にいち早く気づき対応することができるため、体調管理にも役立ちます。
汚れた空気は気管や粘膜を傷めるので、定期的な換気も忘れずに。対角線の窓を開放し、2時間に1回の換気が理想とされています。
ポイント4温度差を減らす
温かい空気は天井に、冷たい空気は足元にたまりやすい性質があります。エアコンの風向きを下に設定することや、サーキュレーターや空気清浄機などを使って空気をかきまぜることも効果的です。
部屋から部屋へ移動する際にも温度差が生じます。特に体が露出する入浴時などは、この温度差によってヒートショックを起こしやすく、注意が必要です。次の健康コラムでは、「住まいの快適な室温と湿度 ~ヒートショックについて~」をお話しようと思います。
作成 : 大東建託パートナーズ株式会社 人事部健康経営課 保健師 飯塚祐美恵
監修 : 大東建託パートナーズ株式会社 人事部健康経営課 産業医 林幹浩
(株式会社ビスメド 労働衛生コンサルタント)
(2020年1月31日)
●参考資料
環境省WARM BIZとは:https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/warmbiz/about/(2020年1月9日アクセス)
東京都福祉保健局 室内空気環境の管理:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/kankyo_eisei/jukankyo/indoor/kenko/kenkai_bunyatosisin.files/web_bunya1.pdf(2020年1月14日アクセス)
●産業医と保健師による情報の提供は、診断・治療行為ではありません。診断・治療を必要とする方は、適切な医療機関での受診をおすすめいたします。また、掲載内容は作成者個人の見解によるものであり、全ての方への有効性を保証するものではありません。当コラムで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いかねます。
ヒートショックという言葉を耳にすることがあるのではないでしょうか。ヒートショックとは、暖かい部屋から寒い部屋への移動など温度の急な変化が体に与えるショックのことです。まわりの急激な温度変化によって、血圧が大きく変動し、脳や心臓へ十分な血液が流れなくなってしまうことでヒートショックが引き起こされます。ヒートショックによる症状は、血圧が急激に大きく上がったり下がったりすることでフラフラすることです。さらに重い症状になると、失神したり、心筋梗塞、不整脈、脳梗塞などを起こしたり、それらが入浴中に起こることで、溺れてしまう危険性も高くなります。
寒い冬を快適に過ごす方法として、入浴も有効な手段ですが、入浴時の温度差には注意が必要です。冬季の入浴による心肺機能停止者数は夏場の約11倍と非常に多くなっています。特にヒートショックが起きやすい入浴時も、脱衣所や浴室を暖かくするなど工夫することで予防できます。
ポイント1入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう
暖房器具の使用や、シャワーを活用したお湯はりも効果的です。高い位置に設置したシャワーから浴槽へお湯をはることで、浴室全体を暖めることができます。
ポイント2湯温は41℃以下、お湯に浸かる時間は10分までを目安にしましょう
熱いお湯につかると血圧を大きく変動させるので注意しましょう。かけ湯は、心臓から遠い手や足からがおすすめです。
ポイント3浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう
浴槽から出るときは、手すりやへりを使ってゆっくり上がりましょう。
ポイント4夕食前・日没前の入浴を心がけましょう
日中は日没後に比べ、外気温が比較的高く、脱衣場や浴室がそれほど冷え込まないのでおすすめです。
ポイント5食後すぐ、飲酒後、服用後すぐの入浴は避けましょう
体調が悪いときはもちろんのこと、精神安定剤、睡眠薬などの服用後の入浴は危険ですので注意しましょう。
ポイント6入浴する前に同居者に声をかけて、見回ってもらいましょう
入浴前に同居者に一声かけ、同居者はいつもより入浴時間が長いときには入浴者に声をかけることで、早期発見にもつながります。
生活習慣病の方は注意が必要です。高血圧の方は、血圧の激しい上下変動により、低血圧症が起こりやすく意識を失うことがあります。糖尿病、脂質異常症の方も、動脈硬化が進行していることがあるため、急激な温度差による血圧の変化で血管にストレスがかかり脳卒中や心筋梗塞をおこす危険性が高まります。
また、高齢者は血圧変化をきたしやすく、体温を調節する力が低下しているため特に注意が必要です。
住まいの室温・湿度を上手にコントロールして、寒い冬も健康で快適にすごしましょう。この健康情報が皆様のお役にたちますように。
作成 : 大東建託パートナーズ株式会社 人事部健康経営課 保健師 飯塚祐美恵
監修 : 大東建託パートナーズ株式会社 人事部健康経営課 産業医 林幹浩
(株式会社ビスメド 労働衛生コンサルタント)
(2020年1月31日)
●参考資料
STOPヒートショック:https://heatshock.jp/ (2019年11月13日アクセス)
消費者庁News Release(2018年11月21日)冬季に多発する入浴中の事故に御注意ください
地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 冬場の住居内の温度管理と健康について 2013年12月2日:https://www.tmghig.jp/research/release/cms_upload/press_20131202.pdf(2019年12月7日アクセス)
●産業医と保健師による情報の提供は、診断・治療行為ではありません。診断・治療を必要とする方は、適切な医療機関での受診をおすすめいたします。また、掲載内容は作成者個人の見解によるものであり、全ての方への有効性を保証するものではありません。当コラムで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いかねます。
日々の暮らしの中でくしゃみや鼻水が止まらなくなることはありませんか。目のかゆみも止まらず、ひょっとしてアレルギー?!もしかしたらハウスダストが原因?と考えたことはありませんか。 住まいにはアレルギーを引き起こすハウスダストが潜んでいることがあるのです。
ハウスダストとは家の中にあるホコリに含まれるダニの死骸や糞、人や動物のアカやフケ、毛、カビ、細菌、花粉等小さなゴミのことをいいます。そして、このハウスダストが引き起こすアレルギーをハウスダストアレルギーといいます(アレルギーとは、体が異物を外に出そうとして起こる過剰反応のことをいいます)。
ハウスダストアレルギーの症状は人によって様々ですが、ハウスダストがホコリと一緒に空中に舞い上がり、目や鼻などの粘膜に付着すると、目が痒くなったりくしゃみや鼻水が止まらなくなったりします。気管支に吸い込んでしまうと、激しい咳や、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という呼吸の音、呼吸困難などの症状が出ることがあります。また、ハウスダストが皮膚に触れると、皮膚に炎症が起き、かゆみや発疹、乾燥を引き起こすこともあります。
それら症状が軽い場合、風邪と勘違いすることが多いかもしれません。特にお子様がまだ小さい時は症状をうまく伝えることができないため、周りの大人がよく見てあげることが必要になってきます。
ハウスダストアレルギーの症状かもしれないと思ったらどうしたらいいのでしょうか。次の健康コラム「住まいの アレルギー対策 ~ハウスダストアレルギーだと思ったら~」でお話ししようと思います。
作成 : 大東建託パートナーズ株式会社 人事部健康経営課 保健師 印東桂子
監修 : 大東建託パートナーズ株式会社 人事部健康経営課 産業医 林幹浩
(株式会社ビスメド 労働衛生コンサルタント)
(2019年10月11日)
●参考資料
千葉県医師会:https://www.chiba.med.or.jp/general/topics/medical/medical_15.html (2019年9月27日アクセス)
東京都アレルギー情報Navi:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/allergy/ (2019年9月18日ア
クセス)
東京都保健福祉局:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/kankyo_eisei/jukankyo/indoor/index.html (2019年9月18日アクセス)
東京都福祉保健局(2018):健康・快適居住環境の指針 ―健康を支える快適な住まいを目指して―平成28年度改訂版
東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課(2018):健康・快適居住環境の指針 室内の環境整備とアレルゲン対策
東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課、公益社団法人東京都医師会(2018):「住まいとアレルギー」 -室内のアレルゲン対策―
東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課(2018):住まいの中のアレルゲン対策 ~ぜん息の発作や悪化を防ぐために~
タケダ健康サイト:https://takeda-kenko.jp/navi/navi.php?key=hausudasuto_kuchi (2019年9月18日アクセス)
ダスキン:https://www.aims-e.com/kaiteki/housedust (2019年9月18日アクセス)
●産業医と保健師による情報の提供は、診断・治療行為ではありません。診断・治療を必要とする方は、適切な医療機関での受診をおすすめいたします。また、掲載内容は作成者個人の見解によるものであり、全ての方への有効性を保証するものではありません。当コラムで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いかねます。
まずは、かかりつけ医に相談しましょう。もしかかりつけ医がまだ決まっていない場合は、大人ならば内科を、お子様ならば小児科を受診しましょう。ハウスダストアレルギーによる症状は1つでないことが多いのですが、もし症状が1つの場合は、鼻水が止まらなければ耳鼻科を、目の痒みや赤みが止まらなければ眼科を受診しましょう。
通常の検査や治療で良くならない場合、もしくは、専門的な検査や治療が必要な場合などは、アレルギーの専門医を紹介されることもあります。
もしハウスダストアレルギーと診断されたら、投薬治療とは別に、ハウスダストを「増やさない」「取り除く」工夫が大切になってきます。また、毎日の習慣がハウスダストアレルギーを予防するカギになります。
ポイント1湿度の管理はしっかりと
ダニは湿度の高い環境を好みます。温湿度計を準備して、適切な換気や除湿通気で室内の湿度が60%を超えないようにしましょう。押し入れやタンスの中等の湿気がたまりやすいところには除湿剤を使用したり、意識して風を通したりすることをお勧めします。また、ダニの好む寝具は布団乾燥機や天日干しで乾燥させた後、布団用掃除機をかけましょう。
ポイント2生息場所を減らそう
ぬいぐるみやクッション等、ダニが潜り込めるものを減らしましょう。その他のダニの好む場所はカーペットや足ふきマット、畳、寝具と言われています。
ポイント3餌を減らそう
ダニの餌となるホコリやチリが溜まらないように、室内の整理整頓や清掃を心掛けましょう。ホコリ1gの中にダニが2,000匹いるというデータもあるそうです。また、カビもダニの餌になります。カビの原因になりやすい結露にも気をつけましょう。
ポイント4アレルギー症状や病気のある方は、ペットを飼育する前に主治医へ相談を
残念なことにペットの毛やフケ、糞、唾液などはダニの餌になるだけでなくアレルゲンになり得るため、ペットを飼育する場合は、主治医に相談しアレルゲンを減らすための対策を行いましょう。
ポイント5掃除はこまめに
フローリングモップや掃除機、ほうき等をかけたり、ウエットシートや雑巾で水拭きをしたりしましょう。掃除の際は、ダニの死骸や糞を含むホコリが舞い上がらないように一方向にできるだけ静かに行いましょう。空気清浄機で空気中の浮遊物を除去することも有効です。また、エアコンのフィルターや24時間換気のための吸気口を定期的に掃除することで、ダニの餌であるカビの発生を取り除くことができます。
ポイント6定期的な洗濯を
カーテンやラグ、クッションカバー等水洗いできるものは洗うことにより、ダニの死骸や糞、ホコリ等を取り除きましょう。寝具の丸洗いもおすすめです。
作成 : 大東建託パートナーズ株式会社 人事部健康経営課 保健師 印東桂子
監修 : 大東建託パートナーズ株式会社 人事部健康経営課 産業医 林幹浩
(株式会社ビスメド 労働衛生コンサルタント)
(2019年10月11日)
●参考資料
千葉県医師会:https://www.chiba.med.or.jp/general/topics/medical/medical_15.html (2019年9月27日アクセス)
東京都アレルギー情報Navi:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/allergy/(2019年9月18日アクセス)
東京都保健福祉局:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/kankyo_eisei/jukankyo/indoor/index.html(2019年9月18日アクセス)
東京都福祉保健局(2018):健康・快適居住環境の指針 ―健康を支える快適な住まいを目指して―平成28年度改訂版
東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課(2018):健康・快適居住環境の指針 室内の環境整備とアレルゲン対策
東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課、公益社団法人東京都医師会(2018):「住まいとアレルギー」 -室内のアレルゲン対策―
東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課(2018):住まいの中のアレルゲン対策 ~ぜん息の発作や悪化を防ぐために~
タケダ健康サイト:https://takeda-kenko.jp/navi/navi.php?key=hausudasuto_kuchi (2019年9月18日アクセス)
ダスキン:https://www.aims-e.com/kaiteki/housedust (2019年9月18日アクセス)
●産業医と保健師による情報の提供は、診断・治療行為ではありません。診断・治療を必要とする方は、適切な医療機関での受診をおすすめいたします。また、掲載内容は作成者個人の見解によるものであり、全ての方への有効性を保証するものではありません。当コラムで提供する情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いかねます。
